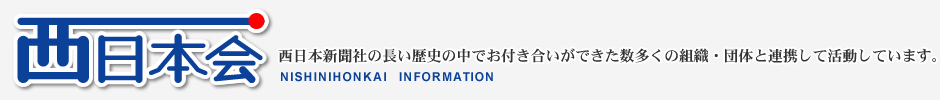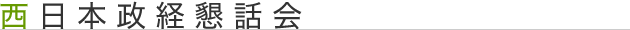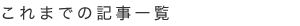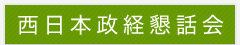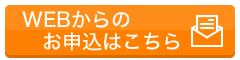筑豊第606回 トランプ政権と停戦の行方は

西日本政経懇話会3月例会が14日、飯塚市であり、慶応大法学部教授の錦田愛子氏が「トランプ政権とイスラエル・ガザ戦争の行方」と題して講演した=写真。要旨は次の通り。
1月、パレスチナ自治区ガザでの停戦合意が成立し15カ月間続いた(イスラエルとイスラム組織ハマスの)戦闘が休止する急展開を迎えた。トランプ氏は「われわれが関与しなければ、交渉は成立しなかっただろう」と述べ、自身の手柄だと誇った、と報じられた。
なぜ、トランプ政権になり急展開したのか。歴史に残る大統領として功績を求めるトランプ氏にとって、その一つが停戦だった。
トランプ氏は第1次政権時代、イスラエルと中東諸国との間で国交を樹立させるなど、イスラエルに大きな恩恵をもたらした。同国を一押しすれば停戦できるとみられる中、米国はイスラエルに圧力をかけられる唯一の存在となっていた。
現在、ガザ地区では6割の住宅と道路が破壊され、経済規模が開戦以前の水準まで回復するのに70年以上かかるとされる。支援物資の搬入の可否は、力のあるイスラエル側の裁量次第で電力供給も中止されている。予断を許さない状況だ。
地震や津波などの災害復興に尽力してきた日本は、ガザ地区の復興においても技術を生かせる。中立的に地道な支援を行う、信頼できる国として関わっていくことができるだろう。 (吉田真紀)
2025年(令和7年)03月15日(土)