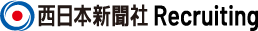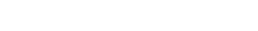新聞ファンを増やし
経営を支える
販売局 販売部 二島 朋美
2016年入社
※所属部署は取材当時のものです。
販売部の仕事は九州内に約400ヶ所あるエリアセンター(販売店)の業務を管理するとともに販促企画の立案、実践を重ねて読者の維持・拡大を図ることです。また大雪や台風はもちろん地震など自然災害が発生した場合でも読者のもとに新聞を届ける使命があります。一方で、あらゆるところで新聞の面白みや魅力を発信し、西日本新聞のファンを増やすことで、新聞社の経営を支える役割を担っています。日頃は担当地区のエリアセンターを毎月訪問し、業務体制の確認や営業方針の打合せ、また新聞を活用したワークショップ「まわしよみ新聞」の提案などを行っています。

ソフトバンクホークスやアビスパ福岡の試合会場で実施するPRイベントが一番面白いと感じました。新聞販売手法は以前のような訪問販売主体から、近年は地域のイベントやお祭り会場にPRブースを出店するイベント手法に切り替わりつつあります。時代の変化とともに価値観が多様化するのは当然ですが、報道機関としての役割を果たすためにも新聞の魅力をより多くの人に伝え、新聞のある暮らしの提案をしていかなければと思います。
記者が取材、編集して作った新聞をエリアセンターが配達してこそ新聞は商品となります。最前線で読者と接しているエリアセンターとともに新聞と読者を繋ぐ役割を担う販売部の仕事にやりがいを感じます。
また、創刊140周年を記念して作成したPR用リーフレットの表紙に先輩女性部員とともに起用され、バイクに乗って配達する姿が掲載されました。エリアセンターの方々が販促活動として九州各地で配布してくれていると考えると身が引き締まる思いがした貴重な経験となりました。

最大の試練はこれからだと思います。私は大学時代から新聞が好きで、地域のコミュニケーションツールとして新聞の活用に取り組んできました。それが西日本新聞社を目指すきっかけになりましたが、入社以降は新聞業界の厳しい現状を知る日々が続いています。若年層を中心とした新聞離れの現状にどう対応するかなど、社内のみならずエリアセンターとともに考えることがたくさんあります。
情報の扱いが紙媒体中心からネット主流の時代に移り変わった現在、新聞の存在価値をどう示していくか。明確な答えはまだ見つかりませんが、日本独自のシステムである戸別配達網は守らなければと考えます。私自身は新聞に無限の可能性を感じています。理想やビジョンを描きながらも、まずは販売部員として一人前になることが当面の課題です。
女性販売部員は私を含め2人しかいませんが、女性の時代と言われるいま、女性ならではの視点が求められることが多々あります。最大の試練が訪れた時、女性ならではの視点を武器に乗り越えたいと考えます。

毎日外に出ている分、休日は家の掃除や洗濯をして、撮りためたドラマを観たり、数日前の新聞連載をじっくり読み返したりして家でのんびりと過ごすこが多いです。自宅近くの大濠公園で優雅に運動しようと購入したロードバイクは数回乗って部屋のインテリアになってしまいました。また、2週間に1回程度は車で約1時間の福岡県宮若市の実家に帰り、自然の空気を吸ってリフレッシュします。
大学時代から地元のまちづくりに関わっていたこともあり、地元のイベントのお手伝いに行ったり、世代を超えた地域の方たちとの交流で楽しんでいます。写真は、新聞を使ったワークショップ「まわしよみ新聞」に参加した時の写真です。老若男女新聞を読んで、気になる記事を切り抜き、意見交換をして最後に壁新聞を作りました。

販売部ではエリアセンターとともに「金婚夫婦表彰式」や「がん患者へタオル帽子を贈る運動」、また「車いす送迎車を贈ろうキャンペーン」に取り組んでいます。新聞を届けるだけでなく、西日本新聞を支えてくれている読者の方々との繋がりを大切に考え、地域貢献活動という形で関わりを深めている姿が西日本新聞社の魅力だと考えます。
新聞という媒体と戸別配達網という独自のサービスを活用すれば、実現可能なことはまだたくさんあると思います。新入社員にもチャンスとチャレンジを与えてくれる社風があるので、就活生のみなさんにはぜひ「新聞への想いと自由な発想」を持ってぶつかってほしいと思います。
新聞社は男性社会というイメージが強いかもしれません。実際に販売部には私を含め2人しか女性がいませんが、同じビジネス部門である広告局や企画事業室には女性社員も多く在籍しており、それぞれが活躍しています。男性社員の育児休暇取得率も上昇しており、産休・育休を経て職場復帰する女性社員も多いです。これからも時代に合った働き方改革が進み、働きやすい環境が整備されていることを感じます。

「 新聞は配達されてこそ商品になる。会社と読者をつなぐ仕事にやりがいを感じる 」